更新:2023/07/20
10㎝浮上と1㎝浮上の違い
超電導リニアが10㎝浮上して走るのは、地震が多く地盤の弱い日本ではそのくらい浮かさないと安全に高速走行ができないからといわれていると思います。常電導方式の1㎝は日本には適していないと。
超電導リニアの場合、停電して、さらにクエンチなどが起きた、最悪の場合、車体が墜落します。常電導でも停電して、車上の電源がアウトになれば墜落します。墜落する距離は違いますが…
そこで、墜落する高さが1㎝と10㎝の場合を簡単な実験で比べて見ました。小学生や中学生の皆さん、夏休みの自由研究にいかがですか?
用意するものは、小皿などセトモノの器、同じ卵パックから生卵2個、モノサシ。やり方は簡単。1つの卵は1㎝の高さから、もう一つは10㎝の高さから小皿や器の中に落とします。
1㎝から落とした卵は

10㎝から落とした卵は

結果は、高いところから落とした方が卵の壊れ方がひどいということ。これは物理の法則によるもの。超電導リニアと常電導方式との間でも同じことがいえるはず。
さて、著名な鉄道評論家である川島冷三さんは『徹底詳解 リニア中央新幹線のすべて』(廣済堂出版、2012年)の中で、上海のリニアモーターカー(トランスラピッド)や名古屋のリニモ(HSST)などの常電導方式について次のように述べています。
(常電導方式では)重力と吸引力のバランスで浮上しているのだが、バランスが崩れて重力のほうが勝ってしまうと、軌道と浮上装置が離れてしまうから、余計に吸引力が落ちてしまい軌道と車両が接触してしまう。設計的にはフェールセーフになっていないのである。(p29)(補足説明)
川島さんは、それに対して超電導リニアはこういう仕組みだからという部分を明確に対比させて書いていないんですが、一般的に説明されているのは:
- 超電導リニアは基本的には磁石同士の反発力を利用しているので、何も制御をしなくても、ガイドウェイの中で、車体の重量とか車体に働く遠心力などと自然に釣り合う位置を走るが、
- 常電導では吸引力を利用するので、吸引力というのは何もしなければ「ひっついて」しまうので、エレクトロニクス技術を用いて、浮上量を常に計測して、電磁石に流す電流を調節して一定の浮上量を確保することが必要になる
川島さんが「重力と吸引力のバランンスで浮上」といっているのは「エレクトロニクス技術を用いて、浮上量を常に計測して、電磁石に流す電流を調節して一定の浮上量を確保する」という部分です。
よくよく考えてみると、超伝導でも、ガイドウェイ側の浮上コイルは比較的簡単な構造なのですが、超電導磁石はかなり複雑な構造です。現在のところ配管のある冷凍機や真空容器なんかがあって、それらが完全に機能していないと、たとえばクエンチなど磁力がなくなる現象が起きたりと、超電導磁石の磁力が保てないのです。また、時速150㎞以上の速度で走っていないと十分な浮上力をえることができません。単純な磁石同士についての反発力と吸引力の性質の比較だけで優劣は判断できないはずです。
つまり、常電導も超電導も、何か仕組みあって動いているという点は、同じなのです。重要なことは、超電導も常電導も、その仕組みを構成する部品とか技術の信頼性です。
超電導磁石を低温に保つために、超電導の配管がある冷凍機や低温を保つための魔法瓶のような容器を使ったりします。超電導磁石については、超電導材料から細い電線を作ってきちんと巻く技術や、より高い温度でも超電導になる材質の開発など、けっこう面倒くさい問題もあるはず。「超低温に保つ技術と超電導磁石そのもの技術」と、「エレクトロニクス技術」のどちらが信頼性が高いかということでは、世間一般、あらゆる分野で広く普通に利用されているエレクトロニクス技術に軍配が上がるのは明らかだと思います。
実際、超電導方式も常電導方式もまだ開発段階にあった80年代に、実現はしなかったのですが、アメリカのロサンゼルスとラスベガスの間を結ぶ磁気浮上鉄道構想でトランスラピッドが選ばれたことがありました。選択理由はエレクトロニクス(当時はソリッドステート技術といっていた)の信頼性は実証されているが超電導は未知の技術だという理由でした(補足説明)。
こうしてみると、常電導の浮上量の1㎝のほうが墜落した時の衝撃力が小さいというのはけっこう利点じゃないかと思いませんか。また、磁力の働く間隔(エアギャップ)が少ない方が効率が高くなるので、より少ない電力消費で走行できるという利点もあるわけです。
では地震との関係はどうなのか。地震で軌道が変形した時に10㎝の余裕があったほうが安心といわれています。1㎝では心配だと。
超電導リニアで鉄道のレールにあたるのはガイドウエイの側壁部分です。側壁部分は高架橋と一体構造のものではなくて、ついたて状(逆T字型)の長さ約12.6m、高さ約1.3m、最大幅が約60㎝(?)程度のコンクリート製品です。これを高架部の上に立ててボルトでとめる構造です。コンクリート製品ですから、地震で生じる変形といえば、割れるか、ヒビが入るか、隣同士の側壁がずれてしまうといったことが起きると思います。
だから、10㎝浮上しないと安心できない。
参考として、次のような説明もあります。「反発方浮上式は、自然な電磁誘導作用によって地上コイルに流れる電流と車上の界磁磁石の力で支持・案内を行う。したがって、制御システムが不要となり、ある速度以上であれば、常に安定な浮上・案内力が得られる点が利点である。また、この方式では、自然な浮上力によって浮いているため、浮上高さの振動などが起こった場合でもその制御はできない。そのため、車上コイルが振動しても大丈夫なように、浮上ギャップ長を前述の10㎝と大きく設計するのである。」(「鉄道車両技術のア・ラ・カルト 第18回 超電導磁気浮上方式鉄道」、近藤圭一郎、『鉄道ジャーナル』2017年1月号)
常電導ではレールにあたる部分は、断面の形はぜんぜん違いますが、鉄のレールです。コンクリート製品と比べて、変形のしかたは、より滑らかな感じなんじゃないかとは思いませんか。隣同士の連続性はどうでしょうか。
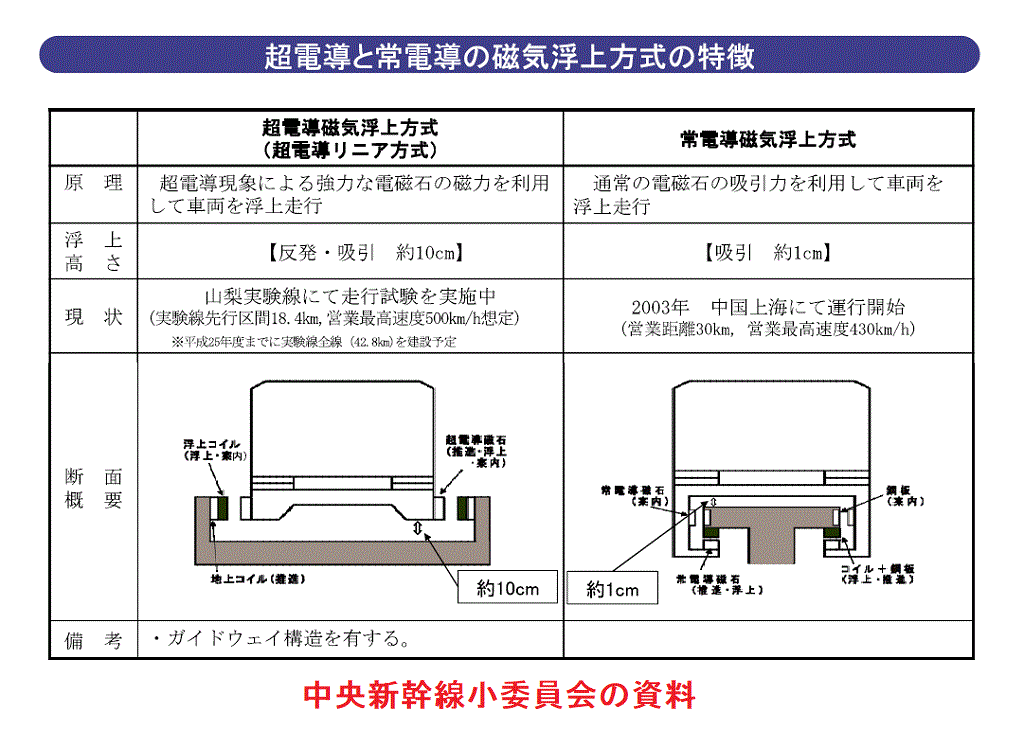
(拡大表示) たぶんこの説明図は国交省が作成したものだろうと思います。常電導の図解で「約1㎝」とされる部分(最低地上高)は15cmです。なお、上海の路線で2002年11月に時速501㎞で走行しており、車体自体は時速500㎞運転ができる性能があります。「備考」に超電導については「ガイドウェイ構造を有する」としていますが、常電導は空欄になっている。
より正確な図解は下の図。車体の「そり」(スキッド、図中「8」)とガイドウェイの隙間が1㎝です。図の車体から出ている腕の先に電磁石「5」があって、ガイドウェイ側の推進コイルの巻かれている鉄のレール「3」の間に吸引力が働く。
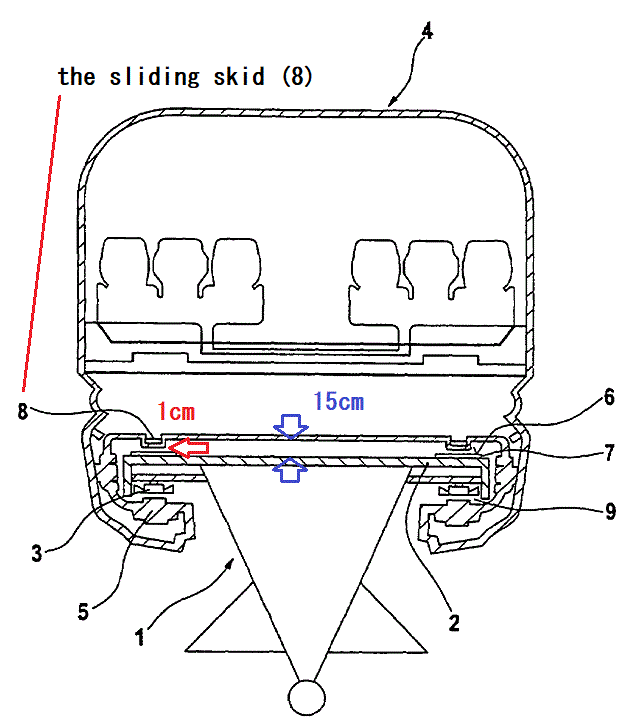
常電導のトランスラピッドの特許関連の図解から。
常電導はガイドウェイに車体がしがみつくような構造になっていますね。そこまでみて、どちらが地震に対して強いか考えてみるのもよいのではないかと思いますね。浮上用コイルと台車の間、台車と車体の間にはサスペンションがついているので、建築物の免振構造にも似た構造ですから地震の時に車体が軌道へ与える衝撃も少なくなるはずです。
だから、1㎝でまにあう。
参考として、次のような説明もあります。「コイルの電流制御で浮上高さを自由に制御できるため、… 浮上ギャップ長を1㎝程度に小さくすることができる。そのため、地上の推進コイルと車上の界磁磁石とのギャップ長も短く保つことができ、回転電動機同様、鉄芯によって磁束を集中させて十分な推進力を得るという方式が実現できる。」(「鉄道車両技術のア・ラ・カルト 第18回 超電導磁気浮上方式鉄道」、近藤圭一郎、『鉄道ジャーナル』2017年1月号)
超電導リニアは地上を走る部分(明り部)ではほとんどの場所で防音防災フードが設置されます。これもコンクリート製品で、地震のとき、ヒビがはいってコンクリート片が落下するなんてことがあるのかないのか。
地震が発生したら、早期に地震を検知して、急停車するという対策が考えられているわけで、その場合、運転速度が遅いほど安全性が高いはずです。そもそも、500㎞もの速度で走ること自体が地震国ではアブナイということなんです。高速列車の速度は300キロとか250キロで我慢しなくてはならない。そうなれば、超電導も常電導も必要ないということになりますね。
細かい点について専門的な知識に基づいた検討が必要なことは当たり前なんですが、10㎝と1㎝と比べて10㎝だから地震に対して有利という説明に、少しは疑いを持った方がよいというのがいいたいことです。
なお、超伝導リニアでも、「震度6以上の大地震では最大加速度の振動を受ける数秒間に、案内ストッパ輪が左右のガイドウェイに数回、ほぼ確実に接触する」という指摘もあります。
「磁気浮上列車の地震動応答」、阿部修治、『武蔵野大学数理工学センター紀要』202年3月
トランスラピッドの構造を見ればあきらかですが、ガイドウェイと電磁石との間の距離は際限なく広がっていくわけじゃなく、約2㎝が最大です。トランスラピッドは超電導と違って「やんわり」と「そり」で着地して、「そり」とガイドウェイの間の適度の摩擦ですぐに減速が始まります。駅で停止している間は最大限の2㎝までギャップが広がっているんですが、発車する前に、そこからエイヤッと1㎝持ち上げるわけですから、距離が広がるほど吸引力が弱くなるから「フェールセーフになっていない」なんてことは、単純な100円ショップで25個セットで売ってるような永久磁石についていえることで、川島さんの指摘は、仕組み全体として見るなら、完全に的外れです。
7月21日 補足
ジェラルド・K・オニール著、牧野昇訳『六つの超大技術市場―テクノロジー・エッジ』(新潮社、1985年、原著は1983年刊)の p165 「現代のソリッドステートのエレクトロニクスは非常に信頼性が高く、また利用する力も並列電流によって簡単に供給できるので(*)、実際は極めて安全である。引き合うマグレブ(吸引方式、EMS、常電導)の実用面における安全性は実証されている」、p166「低温技術が商業的に大々的に利用された例はこれまでのところないので、バイヤー予備軍は力学的マグレブ(EDS、超電導リニア)は引き合うマグレブに比べて開発にまだ時間がかかりリスクも高そうだと見ている」は当時の一般的な見方が書かれた部分。
*:「利用する力」を磁力、「並行電流」は2つの電線に同方向に流れるとき、電線の間に吸引力が働くという現象についていってると解釈すると、おそらく、「超電導方式=力学的マグレブ(EDS)では、まず推進するための電力を供給し、ある程度高速になってやっと車体を持ち上げるほどの磁力が生じるが、常電導では電磁石のコイルに電流を流すだけで磁力が発生して車体を持ち上げることができる」という位の意味かと思います。
ラスベガスとロサンゼルス間の構想について、ラスベガス市は1982年にバッド社とベクテル社に調査を依頼。バッド社は調査の一部をトランスラピッド・インターナショナル社に委託(トランスラピッドの海外への売り込みが始まっていた)(p178~179)。いくつかの鉄道方式や超電導の日本の国鉄方式とトランスラピッドを比較検討した結果、「日本の国鉄が開発している力学的マグレブ・システムは、高度過ぎて1980年代に建設するのは不可能であろうと判断を下し、TVEのTR-06型の引き合うマグレブ・システムが実用的であり、研究に値する、という結論に達した。」(p179)。
EOF