更新:2025/05/03、補足 2025/05/07、補足 2025/05/08
要対策土活用の説明に「ひじき」を持ち出すJR東海
※ 誤解をあたえる可能性のある部分もあったので、整理しました。
大切なことは、危険だから他の土砂と別にして扱う決まりになっている「要対策土」なのですから、たとえ厚いコンクリートで囲ったとしても、人の住む場所でかつ地下水位の高い地下に埋めてしまうのは止めるべきであって、事業者であるJR東海の都合で埋めるのに、周囲の住民に対して、ヒ素が漏れたとしても心配することはないよ、気にするほどの問題じゃないですよと、危険が少ないような印象を持たせるような説明はすべきでないです。JR東海の説明は、もれることは絶対にないと思うけれど、もれちゃうことがあったとしても、どうってことないよという説明です。
JR東海は、周囲に人が住んでいて、水の利用も多いところの、地下水位の高い場所に埋める駅工事の一部の基礎の中に、基準値を超えるヒ素などを含む要対策土を詰める計画について住民に説明する時に「ひじき」にもヒ素は含まれていると説明。
地下水が含むヒ素は風化した岩石や土壌から溶け出したもので無機ヒ素。つまり要対策土に含まれるヒ素は有毒な無機ヒ素。
無機ヒ素の方が毒性が強く、有機ヒ素にはほとんど毒性はない。
海藻類の中で「ひじき」は無機ヒ素を多く含む(比較的古い時期の書籍には、「ひじき」などの海藻類に含まれるのは有機ヒ素だから問題ないとするものがあるけれど、最近の調査報告書などでは無機ヒ素とするものが多いようです)。
「ひじき」の流通、調理の過程で無機ヒ素の量は減少するので、「調理したひじき」に含まれるヒ素の量でなければならないはず。
日本人の平均的な「ひじき」の摂取量ではこれまでに健康被害は確認できていないが、一部では健康に影響を与える可能性のある量を摂取している場合があると指摘されている。そして、「ひじき」などは食べ過ぎないようにバランスの良い食事に気を付けるべきとされている。
JR東海は、工事に使う要対策土に含まれるヒ素について、それほど心配する必要はないという印象を住民に与えるために「ひじき」の話題を持ち出したと思われる。
「要対策土」は危険性があるものとして区分されたもので、今回の場合はその原因がヒ素を含むことであるので、JR東海の行う工事の方法や基礎の構造が完全なものであるなら、住民への説明では、「ひじき」の話題を持ち出して「それほど心配する必要はない」と説明する必要は本来ないし、するべきでなかった。ヒ素は危険なものとしてだけ扱えばよかったはずだ。
専門家で構成する長野県環境影響評価委員会では、「ひじき」の話題をJR東海は出していないことから、「ひじき」の話題を住民対象には行ったのは、住民をだまそうとする意図があったといっていい。
「ひじき」は「うまい」か「まずい」か
ヒ素やほう素など重金属類を基準値以上含むトンネル残土の活用、JR東海は「要対策土」といってますが、有害残土ですね、これを、建設資材として、JR東海のリニアの工事で使いたいとか、公共事業で使ってもらいたいと、JR東海はいってます。これまで、このことについて、大鹿村と、飯田市では座光寺地区と上郷地区で住民説明会を行いました。その中で、JR東海は、「自然由来の重金属」っていうのはヒ素とかほう素のことですが、「自然由来の重金属」は「自然界に存在するものであり、地殻や食品、温泉水等にも含まれているものです」、「『ひじき』にはヒ素やほう素が含まれています」と説明していました。
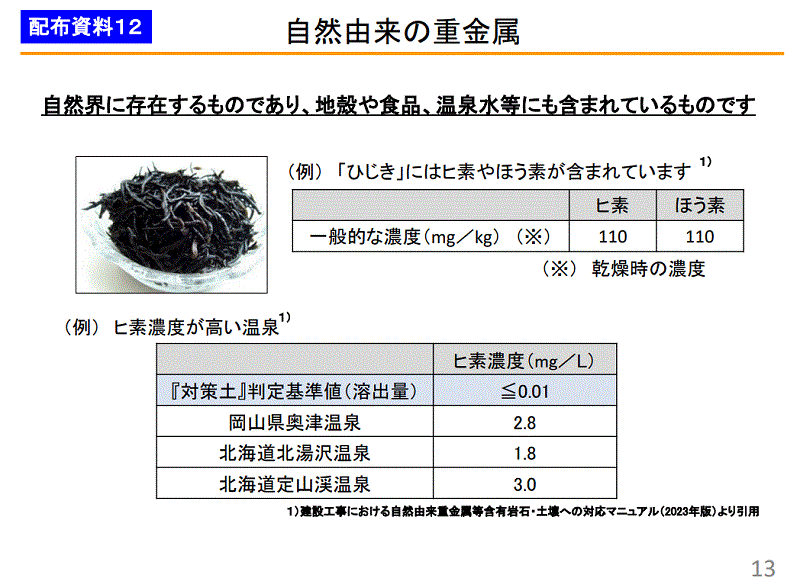
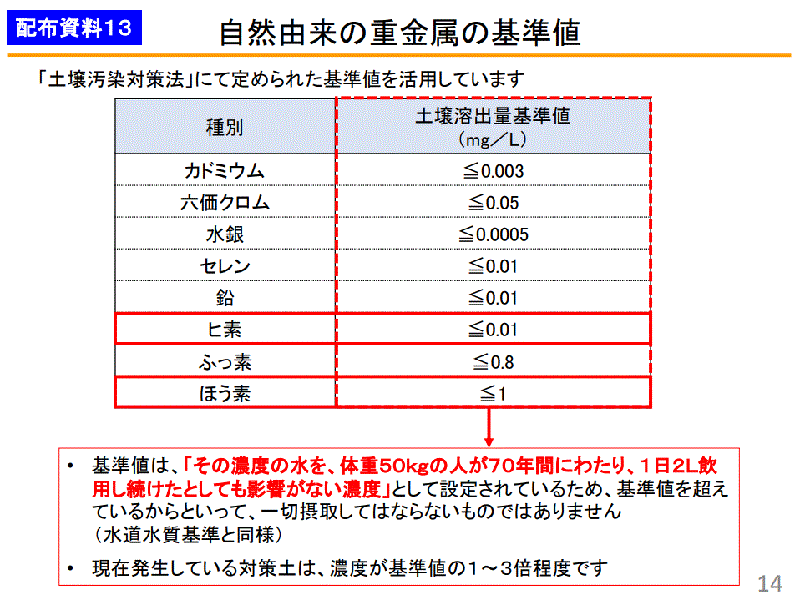
(令和6年2月28日 丹保・北条地区 リニア関連事業に関する丹保・北条地区説明会 > 資料1 リニア中央新幹線事業に関する説明会 (PDFファイル/47.99MB) のp13・14)(※)
「ひじき」や温泉水に含まれる量は1.8~110mgなのに、基準値は、ヒ素は0.01mg以下、ほう素は1mg以下とずっときびしいから、建設資材として使っても安全で問題ないと言いたかったのでしょう。この説明は中間駅の一部になる土曽川橋りょうのケーソン基礎の内部の空洞に要対策土詰める計画についての住民説明会の中で行われたものです。
JR東海がだした環境保全計画に対する長野県の助言が1月27日に公表されました。2ページ目の下のほう「その他」で「ク 橋脚基礎部において要対策土を使用するに至った経緯、使用する要対策土に含まれる物質の種類や濃度、及び要対策土の運搬車両の運行計画台数を環境保全計画書に追記すること。」と、また「コ 当助言を踏まえた環境保全計画書の変更部分をはじめ、新たに見直した計画や対策の内容について、飯田市及び地域住民に丁寧に説明すること。」書いてあります。「物質の種類」について環境保全計画書に書いて、住民にも説明しなさいよと書いている。
環境保全計画書には、p58とp59にそれぞれ1カ所ずつ「ヒ素」という文字は見えます。が、さて、これで「物質の種類」を示したといえるのか。
4月23日の説明会で、要対策土に含まれている「ヒ素」はどういう「化合物」として含まれているかと質問をしてみました。回答した課長は、元素ごとの基準値について説明するだけで、化合物の名前を説明しませんでした。
何が問題なのかというと、「ひじき」などの海藻類に含まれるヒ素は「有機ヒ素」で、数種の本を調べましたが、「有機ヒ素」では中毒は起こさないと書いています。それに比べ「無機ヒ素」は有毒だと。
たとえば、『元素118の新知識 第2版』(講談社ブルーバックス、2023年7月、p192~)では、「ひじき」に含まれるヒ素は有機ヒ素で人が食べてもすぐに尿の中に出てしまう。海藻類に含まれる有機ヒ素は影響がなく、毒性があるのは無機ヒ素と。
『ハンディー版 環境用語辞典』(共立出版、2000年6月、p237)では、海水には無機ヒ素が含まれるが、海産生物には異常に高い有機ヒ素化合物が含まれるのに中毒を起こさないのは、このような有機ヒ素化合物には毒性がないことが明らかと。
『廃棄物処分・環境安全用語辞典』(丸善、2000年2月、p331)では、ヒ素には+3価と+5価の化合物をつくりとか、+3価のAs2O3は猛毒であるとか、ヒ素化合物をセメント固化すると再溶出するおそれがあるなどと。
『図解 土壌・地下水汚染 用語事典』(平田健正・今村聡監修、オーム社、2009年、p131)は、「…一般に地下水または土壌溶出液中に存在する砒素はほぼ砒酸イオンと亜砒酸イオンで、有機砒素はわずかである。自然界の砒素の毒性は砒酸、亜砒酸、有機砒素の順で小さくなる。例えば、海藻に蓄積されるメチル砒素の毒性は無機砒素に比較してかなり低い…」と。
『元素大百科事典 新装版』(渡辺正監訳、朝倉書店、2014年、p555)では、「地下水が含むヒ素のほとんどは、風化した岩石や土壌から溶け出したもの。一部のがんは水のヒ素が原因だった。米国環境保護局(EPA)は2001年、飲み水のヒ素基準値を50μgL-1から10μgL-1に引き下げた」と。
『環境科学辞典』(編集・荒木峻ほか、東京化学同人、1998(1985初版)、p663-664)。「地殻や水質中に存在するヒ素は無機の5価ヒ素が大部分である。無機ヒ素では3価は5価よりも毒性が強く、…」と。
つまり、トンネル残土に含まれるヒ素はほとんどが無機化合物なのだろうと思いますから、中毒を起こさないとか起こす可能性が極めて低い有機ヒ素を含む「ひじき」を、住民の安心感を誘うために、説明に持ち出すのは不適切じゃないかと思います。
住民に対する説明会では「ひじき」を持ち出してきたのに、環境の専門家を委員とする長野県環境影響技術委員会の説明では「ひじき」の話を持ち出していないのは、なぜだか考えて見た方がよさそうです。
JR東海は、工事の認可にあたって、国交大臣から住民に丁寧に説明して理解を得るようにといわれていたと思います。こういう説明の仕方が丁寧といえるのかどうか、かえって、なんかウソついてんじゃないのといえるようなことじゃないかと。
こういったごまかしをする会社が安全な乗り物をつくることが出来るとは思いませんね。東海道新幹線というのは、JR東海は安全を自慢にしてますが、JR東海がつくったわけじゃなくて、基本的な部分は「国鉄」がつくったはずです。
※ 「ひじき」に含まれるヒ素やほう素について「乾燥時の濃度」で示していますが、住民を煙に巻くつもりなのだから、「ひじきの五目煮」に含まれる数値を示した方が良かったのではないかと…。
なお、内閣府の食品安全委員会のサイトにQ&A詳細:ヒジキに含有されている無機ヒ素についてというページがあります。「ヒジキには、無機ヒ素が他の食品に比べ高濃度で含まれていることが文献などで報告されていますが、…」という説明があります。上で紹介した『元素118の新知識 第2版』(講談社ブルーバックス、2023年7月、p192~)は「海産物のヒ素の化学形は無機形であることは少なく、アルセノベタイン(海産動物)、メチルアルソン酸とジメチルアルシン(海産植物)などの有機ヒ素化合物であり…」としています。いずれにしても、科学者や政府がいっていることは、「ひじき」は食べても大丈夫ということで、そういう大丈夫なものと、危険な地中から掘り出した無機ヒ素を比べて、有害なものを無害と印象付けるのは、一般常識としてやってはいけないことでしょう。
補足:2025/05/07
例えば、農林水産省の「ヒジキに含まれるヒ素の低減に向けた取組」では:
ヒ素(総ヒ素)には、有機ヒ素と無機ヒ素があり、そのうち、注意が必要なのは無機ヒ素です。ヒジキに含まれるヒ素は主に無機ヒ素(乾物では総ヒ素含有量に対して約7割が無機ヒ素)ですが、無機ヒ素は水溶性なので、水洗い、水戻し、ゆでこぼし等によって低減することができます。
としています。また、ウィキペディアの「ヒジキ」では:
日本では古くから煮物などの食材とされ、総菜として極めてふつうに使われている。一般的に健康食・長寿食とされていることから、旧敬老の日にちなんで9月15日を「ひじきの日」としている。
また:
2001年10月、カナダ食品検査庁 (CFIA)(英語版) は、発癌性のある無機ヒ素の含有率が、ヒジキにおいて他の海藻類よりも非常に高いという報告を発表し、消費をひかえるよう勧告した[31]。これは複数の調査によって裏付けられ[32]、イギリス[33]・香港[34]・ニュージーランドなどの食品安全関係当局も同様の勧告を発表した。
注[34]の香港特別行政区政府・食品環境衛生局の食品安全と公衆衛生 リスク概要 第17号:ヒジキとヒ素 は:
ヒジキには、特に毒性の高い無機ヒ素が自然状態で高濃度に含まれている可能性があります。一方、海外の研究では、昆布などの他の海藻に含まれるヒ素は、主に毒性の低い有機ヒ素であり、ヒジキに含まれるヒ素よりもはるかに低いことが示されています。…一般的に、無機ヒ素は有機ヒ素よりも毒性が強い…WHOの一部門である国際がん研究機関は、ヒ素を人間に対して発がん性がある物質と分類している。…ヒジキには高濃度の無機ヒ素が含まれているため、比較的少量の摂取でも食物由来のヒ素曝露量を大幅に増加させる可能性があります。さらなる安全性評価の結果、少量のヒジキを時折摂取しても健康に悪影響を与える可能性は低いことが示されました。
としています。
「ひじき」に含まれるヒ素について、ここまで取り上げた情報を読むと、①「ひじき」に含まれるなかでは、有機ヒ素が多いのか、無機のほうか多いのか、あるいは、②他の海藻類に比べると無機ヒ素が多いのかなど、なにか、ちょっと曖昧に思える部分もけっこうあると思います。共通することは無機ヒ素は有毒で有機ヒ素にはほとんど毒性はないという点。かなり昔から、「ひじき」にもヒ素が含まれていることがわかるより前から、石見銀山のような毒薬が知られていた時代以前から、日本人は普通に食べて来たわけです。「ひじき」が原因の中毒があったという話は聞かないから、「ひじき」を食べても問題ないという説明には説得力があると思いますが…
大切なことは
大切なことは、危険性があるので区分して扱う決まりになっている「要対策土」なのですから、たとえ厚いコンクリートで囲ったとしても、人の住む場所でかつ地下水位の高い地下に埋めてしまうのは止めるべきであって、事業者であるJR東海の都合で埋めるのに、周囲の住民に対して、ヒ素が漏れたとしても心配することはないよ、気にするほどの問題じゃないでしょと、危険性の少なさを印象付けるような説明はすべきでないということです。JR東海の説明は、もれることは絶対にないと思うけれど、もれちゃうこともあったしても、どうってことないよという話です。
工学的に妥当(「テキトー」なのかも知れない)であっても、環境の観点では不適切です。それと「予防原則」ということを考えないといけないと思います。
補足:2025/05/08
あたらしく3つ(+1)参考ページを見つけたので紹介します。
国立環境研究所の「環境中のヒ素とその健康影響」(『国立環境研究所ニュース Vol.34,No.3(2015年8月)』に掲載)。
一般財団法人 食品分析開発センター SUNATECの「ヒ素の形態別分析について」。
内閣府の食品安全員会の食品安全確保総合調査実施課題一覧の「形成18年度」の「15」、「ひじきに含まれるヒ素の評価基礎資料調査」(報告書本体は調査報告書【PDF形式:837.29KB】をクリックしてダウンロードして開けます)。
日本ひじき協議会 > ひじきと健康ひじきの鉄・ヒ素について
EOF